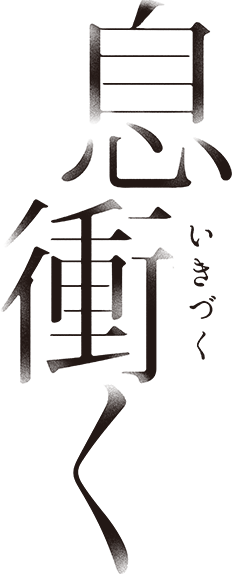上映日誌

【批評】眼差しから遠ざけて、映すという矛盾 Resurrections vol.1-第4回

2018年批評誌『Resurrections vol.1』から第4回目、大澤 恵稔さん(フランス留学中に映画研究、2年前に帰国-2018年時)にご寄稿頂いた批評を掲載いたします。
眼差しから遠ざけて、映すという矛盾
大澤 恵稔(フランス留学中に映画研究、2年前に帰国-2018年時)
彷徨うカメラは三人の寄る辺なさに同調するのだろうか。絶えず動き続けるそれは、何かを追いかける必死さとはどこか違って、むしろ逡巡する一人の人間の姿を思わせる。私はもどかしかった。なぜ、見つめることをさせてくれないのかと。注意をこらすべきはそこに映るものであるはずなのに、どうしてカメラの運動の中に視線を惑わせてしまうのだろうか。放浪するカメラは三人の分身か。あるいは、作り手たちの不決断が侵入してしまったのだろうか。あれこれ考えているうちに問いを封じられてしまったのは、反発を抱く一方でこの映画に引き込まれたせいだった。それでほとんど悔しい気持ちで、私は三度この映画を見に行ったのだが、依然口籠るばかりでいる。この映画の何が私を引き付けたのか、今もよく分からない。ただ、映画から想起されたいくつかの風景だけが、まだ流れ続けている。語ることの出来ないものについては口を噤むべきだが、それでも言葉にしたいときはどうしたらいい。掘り起こされた記憶の断片を辿ることは、私をこの映画へと向かわせるだろうか。そうあることを願って、今私は「息衝く」について書き始める。
2016年の春。フランスは、労働法改正に反対するデモが日に日に激化する中にあって、私の住む町にも火が絶えなかった。大学はバリケードで封鎖され、催涙ガスの白い煙に町は濁り、石畳の道はガラスの破片に覆われた。デモに参加しない私を無言でなじる人がいたが、私は自分の身を守るために外に出なかった。友人の一人が、デモの行進を見つめて言った。「あの群集の中に、カタストロフを待ちわびる人間が一体どれだけ潜んでいるだろう。」と。点在する個の力を集結させるための集団は、個を抑制させることでしか存続出来ない。そうして抑制された個は、各々が持て余した力の矛先を求めて、一つの塊となってしまう。そこへと集い合った最初の理由を忘れて、力を発散することを使命にしてしまう。
あの日の燃える町によく似た光景を、少し前に私は夢の中で再び見た。夜の道を、松明を持った大勢の人々が叫びながら歩いていて、私はその様子を川の反対側から見ている。どこからか、小さな息子を連れた知らない女がやって来て、私にこう言う。「この世で最も危険なことは、信条を持たない信仰を持つことだ。」その夢を見たとき、私は仕事を辞めたばかりで、やっと休息を手に入れたのだが、ひどく虚しい気持ちでいた。所属する場所と、経済的な拠り所を同時になくして、不安で仕方なかった。夢を見たのはそのころだった。「不足によって生きることをしてはいけない。」女の言葉は私にそう聞こえた。「信条を持たない信仰」とは、空虚を満たすことに執着することだ、そう私は思った。不足によって行為することは、私たちの価値観をひっくり返し、私たちを精神の飢餓へと追い込む。空腹を満たすためだけの食事や、肉欲のためだけの愛の行為、そうした行為は私たちを虚しくさせ、虚しさから何度も繰り返される。夢の女は私に忠告していたのだと思う。心細い状態にいた私が、空虚を満たすために他者を求めることをしないようにと、その群れの中に突き進んではいかないようにと、女は私を引き留めようとした。
「息衝く」の主人公たちが抱える苦しみとは、家族と宗教の二つの共同体に渾然一体となることから生まれている。個として起立出来ない彼等は、その存在の曖昧さに喘いでいる。彼等は自身の中に確かなものを見出せず、森山という人間に繋がることで自己を保ってきた。森山について、「ぼくたちが全身で信じてしまえる、そんな人だったんだ。」そう則夫は言うが、彼等は森山を本当に信じていたわけではない。信じるとは、その対象の重みを自身の内に自ずと引き受けたときに、それが存在することを肯定せずにはいられない、そうした受動的なものだ。自身の寄る辺なさから森山を求めた彼等は、彼等の重みを押し付けることは出来ても、森山の重みを彼等の中に引き受けることは出来ない。森山は空っぽの塔である。空っぽだから、彼等はあらゆる意味を森山に与え続け、森山の影と一体になることで、彼等自身を虚しさから救おうとした。彼等は森山を信じていたのではなく、彼等自身を信じたかったのである。則夫はこうも言う。「続けることが何かになるっていうか、そういう実感しか僕らには信じられないからかな。」何かをせずにいられないのは、静止したままでは空虚に耐えられないせいだ。そして不足によって生き続けることは、終わりのない渇きに支配されることだ。だから夢の女は言ったのだ。「この世で最も危険なことである」と。
宗教とは、居場所を求めてすがるものではない。「私」と「私たち」の狭間でためらい矛盾する人間を、宗教は「私」でも「私たち」でもない非人格的なものへと向かわせるものだ。人間から遠ざかり、自身の内に非人格的な一端を発見するときに、人間は自分の存在をありありと感じる。なぜなら非人格的なものとは、人間を超えるものであり、それによって感知される人間は、捉えることの出来ない、その存在の不思議として、何も損なわれず、そのままに浮かび上がるからだ。
彼等三人の不幸とは、神秘的な体験を経ずに信仰へと向かってしまったことだ。そして彼等の抱えるものが「薄い絶望」であることが更なる不幸である。本当の絶望とは、それを誰とも分かち合えない孤独によって、自身の存在をはっきりと知らせるものだ。葉っぱを落とした冬の木が、内側を流れる水によって、寒さに耐えること。それは絶望と希望に似ている。外からの光を完全に奪われたとき、泉はその内側に自ずと湧き出るのだ。しかし「薄い絶望」は何ももたらさず、個になることを邪魔する。一つの共同体を離れる苦しみに比べれば、「薄い絶望」など何でもないのだから。苦しみを避けて、集団の中で曖昧でい続けることを選ぶ人がいるのはそのためだ。「薄い絶望」によって森山を断ち切れなかった彼等にとって、期待を裏切られた森山との再会は幸福な事件であったに違いない。
さて、三人の主人公を、映画は否定も肯定もしない。ふと、動き続けるカメラは、眼差しによって彼等が規定されることを拒むためではないか、そう思った。価値判断を逃れる人間、それとして存在するだけで既にその価値を認められる、人間の存在の尊さに対して、この映画はどこまでも従順であろうとしたのではないだろうか、不意にそう思ったのである。この映画は矛盾する。見るべきものを眼差しから遠ざけて、映し続けるのだから。この矛盾を映画は抱えている、というより、敢えて選び取ったはずなのだが、それが意図的にではなく、本能的な囁きと偶然によって選ばれたような気がしてならないのだ。彼等三人の姿を捉えられない、映画自身が直面した破綻の末に、それでも彼等の姿をそのままに映し出そうとする一貫性によって、映画は自ら矛盾しながら、矛盾する人間に迫ろうとしている。そう思えて仕方ないのだ。
ところで、初めて木村さんを間近に見たとき「男の子の目をしている」と私は思った。そのことを思い出したのは、夢に出た女が、連れていた息子を指してこうも言ったからだ。「この子のように見ることが出来たら、世界はどんなに違うだろう。」子どもとは理屈を介さず、純粋によって大人を超える生き物だ。大人を驚愕させる子どもの純粋に似た何かが、この映画にはある。それゆえに私の反発や問いは全て封じられ、私自身に突きつけられる。そして、純粋さに貫かれて矛盾するこの映画が彷彿させるのは、徒労に終わりながら、それでも善を希求する人間の姿である。その無益なひたむきさは、美でなくして何であろう。