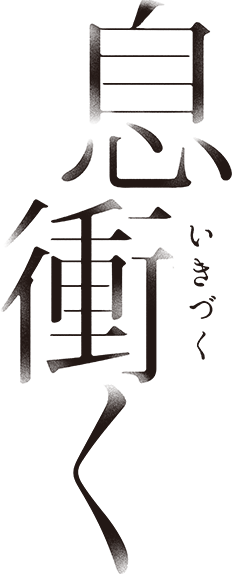上映日誌

【批評】『息衝く』の時間と子供たち Resurrections vol.1-第1回

2018年批評誌『Resurrections vol.1』から第1回目、田中 晋平さん(神戸映画資料館研究員)にご寄稿頂いた批評を掲載いたします。
『息衝く』の時間と子供たち
田中 晋平(神戸映画資料館研究員)
木村文洋の長編第一作『へばの』(2008年)の結末部で、西山真来が演じた紀美の出産の場面を、強烈に記憶している者は少なくないはずだ。幼い頃に母親と兄が家を出てから、彼女は父親と六ヶ所村で生きてきた。ある日、紀美の恋人の治は、再処理工場でプルトニウムの内部被曝に遭う。事故は二人の願っていた未来を奪うが、苦悩の時間を経て、紀美は治の子を産む。その新たな生命の存在が、ひとつの家族や共同体の再生産の物語を超えて、不確定な未来に何かが継承された感触をもたらす。何万年管理せねばならないかわからない、放射性廃棄物とともに。
『へばの』の構想段階では、下北半島の大間が舞台である、相米慎二の『魚影の群れ』(1983年)が参照されていたという(『映画はどこにある:インディペンデント映画の新しい波』フィルムアート社)。そのマグロ漁師である父親と娘の物語(母親は男と駆け落ちした)では、娘が漁師を目指す若い男と去り、父を捨てる。のちに娘は、妊娠して大間に戻るが、夫が海で命を落とし、産まれてくるのが男なら漁師にして欲しいという遺言だけ伝えられる。世代をまたいで、剥き出しの自然に呪縛される人間たちを描いた『魚影の群れ』も、生命の継承という出来事を観る者に問い直させる映画だった。
『へばの』そして『息衝く』の引き裂かれた家族の存在は、電力生産と消費の構造的差別や原発、核燃料サイクル事業への反対運動と地域の分断を浮彫にする。だが、相米の全映画と同じように、木村文洋の映画も「家族」という主題の先にある、生命の連関にこそ眼差しを向けている。監督自身もインタビューでそれを「家族というものは、大いなる時間の流れでの交換、継承だと思います」という表現で語っていた。では、『息衝く』が描く登場人物たちの壊れた家族、あるいは宗教とカリスマの問題、そして、映画内で「薄い絶望」とも語られる政治的閉塞感の根底に、その「大いなる時間」をどのように感受できるだろう。
泰行と則夫、慈たち主要人物の三人は、新興宗教「種子の会」の第二世代、第三世代の信者だった。則夫の母・悦子は、(『へばの』で描かれた)夫と幼い娘を六ヶ所村に残して息子と東京に移住し、種子の会に入信する。そこで則夫は、泰行や慈とともに、皆の兄のような存在となる森山周と出会い、やがて種子の会を母体とした政党で議員として活動する彼を支えていく。その森山が突如失踪してから十年後、参院選で政党から新たな候補を送り出すため、則夫と泰行は、再び選挙活動に奔走する。だが、原発の廃炉プランを掲げようとする切迫感を伴った彼らの行動(ある信者の家の前で則夫は、「僕たちの世代が諦めたらもう終わりですよ」と呼びかける)は、森山の意志を継承したいために、不在のカリスマへの依存を強めていく。一方、親が熱心な信者だった慈は、息子・庭郎と二人で暮らしているが、義姉に彼を連れていかれる際に強く抵抗できず、自身の愛情に疑問を抱く。その背景には、自殺した慈の母親の記憶が潜んでいる。
上記のように深く過去に囚われた人物たちは、則夫の台詞を借りるなら「生きる」とは何か、愛する者と人生に向き合う方途を忘れている。しかし、『息衝く』の時間構造を、このように過去が現在を、死者が生者を捕縛している状態から把握するだけでは不十分だ。映画内の時間には、いくつもの亀裂が走ってもいる。導きの糸として、庭郎が一人で公園の滑り台であやとりをする姿や川辺でザリガニを獲って遊ぶ、短いが印象的なショットを挙げたい。そこではベッドで母親に黙って頭を撫でられていた少年と明らかに異なる、彼が生きた固有の時間が刻まれている。そして、同じことは微かだが、例えば森山が登場しない回想、田無タワー傍の団地で少年時代の則夫が泰行にサッカーを教わる場面にも探り当てられる。まだ訛りを残した少年が、寄る辺のない土地で手を差し伸べる親友を得た、かけがえのない記憶。ここに少女の慈が、祭壇の前で俯いたままの母親を残し、玄関を出て眩しそうに空を見上げるショットを加えてもよい。途方に暮れた状況で不意に生まれるこうした時間が、森山という導き手を失った彼らの現在の閉塞感のみに通じない、自力で、あるいは仲間と協働して生き延びる子供の姿を示す。その意味で映画は、庭郎が親子関係の悪循環に陥ることを運命付けられていないように、かつて則夫たちの未来も一つではなかったこと、いまある世界の偶有性を告げているのではないか。
木村が「家族」について述べた「大いなる時間の流れでの交換、継承」も、一方向に流れ、堆積する時間ではなく、むしろその中断から垣間見える出来事だといえる。映画後半、則夫が市役所を辞め、母親と暮らす空間に野宿者の平間を招き、慈を加えて疑似家族的な共同性が実現する。それは悦子の死によって解散させられる一時的な関係だが、結果として、それぞれの存在を変容させる契機になる。葬式後、切り分けた西瓜を則夫に手渡す平間は、「死ぬのをただ待ってるだけの人生」を断ち切り、故郷の九州に帰ると決める。慈も母の自死と向き合うために長年避けてきた父親を訪ねる。こうして過去が解釈の運動に巻き込まれ、彼女たちは死者と対話しながら「生きる」とはどういうことかを探していく(筆者は、このシークェンスで、「死」を目撃するため少年たちが独居老人の家に集まる『夏の庭 The Friends』(1994年)を想起したが、こうした人間の変容は、『息衝く』のパンフレットで杉田俊介が土本典昭や大島渚の言葉を引用して記す、映画制作自体の協働経験がもたらす可能性でもあるはずだ)。
では、則夫はどうだろう。彼は再会した森山にも「(十年間)変わっていないのはお前だけだ」と喝破された。だが、『息衝く』のエピローグでは、まさに則夫の変容を示唆する、ひとつの「家族」のイメージが挿入される。それは母の遺骨を抱えて六ヶ所村に帰る、血の繋がった兄妹の再会場面 ではない。動物園で老いた象を眺めている則夫の前に、不意にある家族が現れる。その母親に抱えられた赤子の姿に惹かれる則夫の視線を強調し、映画は終わる。彼はその小さな他者から、悦子や森山の記憶に依存し、宗教/政治活動に没頭するなかで見えなくなった何かを感受している。おそらく、それは『へばの』や『魚影の群れ』と同じ、個としての人間の生・死を超えて、生命が継承されていくその感触や時間の尺度である。もちろん、単に『息衝く』が子供たちの未来を祝福しているというのではない。本作の結末には、「薄い絶望」に覆われた社会の先に待つ、破局的イメージも明示されている。けれども、眼前の危機や閉塞状況に窒息させられない、生命の息衝く力もまた継承されていく事実を、則夫も、そして、木村文洋も見据えている。なぜなら、それは映画の子供だった則夫たちに、あるいは庭郎の姿に、確かに引き継がれてきた力なのだから。