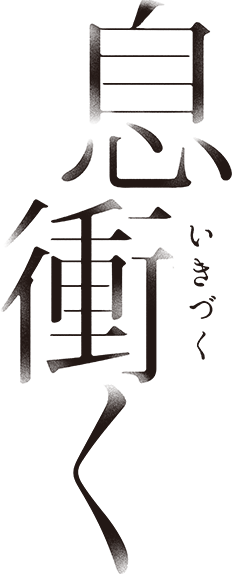上映日誌

2018年2月21日(水)
21日(水)は、18日(日)に続いて、2012年に公開されたオウム真理教の元信者の平田信とその逃亡を助けた女性の関係をモチーフにした『愛のゆくえ(仮)』の上映が行われました。
上映後には本作の宣伝を担当した加瀬修一さんと木村監督が登壇。
加瀬さんが宣伝を引き受けるに至った経緯や公開前後に起きていたことについて、当時を振り返りつつ語りました。
トークは、加瀬さんの挨拶から始まりました。
加瀬「2012年にポレポレ東中野で『愛のゆくえ(仮)』は公開されました。舞台挨拶というと撮影秘話などが語られますが、今日は「宣伝」という立場から、当時何が起きていたのかを振り返りたいと思います。」
続いて加瀬さんより作品の制作経緯についての説明がありました。
加瀬「先日の19日に上映された木村監督が大学生時代に制作した『なしくずしの志』からデビュー作である『へばの』、そして来週公開の『息衝く』は『へばの』で消化しきれなかった想いを形にしたもので、すべて木村監督自身が内包されています。
一方、『愛のゆくえ(仮)』は異色の作品。
高橋プロデューサーの初動で出来上がったものであり、木村監督発の企画ではなかった。しかも年末の逮捕から撮影までわずか4ヶ月程度で、言わば電光石火のスピードで作られました。どうやって『愛のゆくえ(仮)』を自分の作品として捉えて制作をしたのか。それをまず聞きたいです。」
木村「『愛のゆくえ(仮)』は、2009年公開の『へばの』から『息衝く』への制作途中にあって、9割方断ろうと思っていたのですが、2011年の東日本大震災の大晦日に、この映画の主人公のモチーフにもなっているオウム真理教の平田信氏が出頭した理由というのが、震災の中に日本の不条理をみたので、と言ったことが気になりました。
1995年(地下鉄サリン事件)と2011年(東日本大震災)には大きな厄災があったのですが、95年にその中心にいたはずの人が、2回目の厄災で出てきてしまった、ということに対してとても強い印象が自分に残っていました。
個人として絶句し、無力感を覚える大状況に対して、どう対峙し、言葉にしていくのか。
『へばの』から『息衝く』への制作過程で、映画について構想していたことと、主題が重なりました。また、2011年当時の空気感も忘れないうちに映画に刻んでおきたいという想いがありました。」
加瀬「当時、木村監督は良く「部屋の映画」という言葉を使っていました。でも、「部屋の中から世界を見たい」と言われても観念的で良くわからない。
映画のつくり手は思い入れがあるので、観念的な言葉を使いたがるが、宣伝の仕事は監督の思い入れや観念を噛み砕いてわかりやすく世の中の人に伝える仕事。
自分が宣伝の仕事のオファーを頂いたのは4月のことで、まだラッシュ(音が入っていない段階)しかない状態でした。撮影はプロデューサーの高橋さん自身が担当されていて画の力もあって、雰囲気もやりたいことも良くわかったのですが、扱っている題材が責任を伴うという意味で重いし、そしてその責任をどのようにして一緒に監督と負って行けるのだろうか、ということを考えていました。主体となる監督が何をやりたいかわからないと、そこにはコミットできない。
1ヶ月程度は本当に宣伝を引き受けるか、決断しきれなかったように感じます。
結局、前川麻子さんと寺十吾さんにかなりの実力あったこと、そして演劇の別のお仕事でもご一緒させて頂いていたこと、また、高橋プロデューサーも『へばの』でご一緒させて頂いていた、というご縁があった(高橋プロデューサーは『へばの』の撮影を担当)ことから、最初はその3人に対する想いというか義理でこの話を引き受けた、というのが正直な理由です。」
また、加瀬さんは当時の状況について以下のように振り返りました。
加瀬「95年の当時は東京に出て来て自堕落な生活を送っていて、その日も前の日飲んで寝ていたところに、親から「東京ですごいことが起きたらしい」という感じで電話が掛かってきて事件を知りました。留守電にもものすごい数のメッセージが入っていたのです。
80年代はオカルト、95年はサブカルチャーが勢いを持っていた頃で、そうしたことから派生した問題がオウム真理教の事件にすべて凝縮されているように感じていて、95年のオウム真理教事件は、宮崎勤の事件と並んで、そうそう自分の手に負えるものではない、と思っていました。そういうこともあって、宣伝であっても簡単に関わることはできない、と感じていました。」
加えて、加瀬さんは当時の作品に対するバッシングについても言及。
加瀬「当時でさえ自分の携帯電話に「犯罪を美化する作品に加担するのか。人が亡くなっている事件で金儲けをするのか。」という嫌がらせの電話が掛かって来ていました。それは宣伝を引き受ける、ということを決めた時から想定していたことではあったし、ポレポレ東中野さんも同じ覚悟はあったと思います。
普段、ドキュメンタリーなどの啓蒙的な内容の映画を上映する場所で、人殺しを美化するような作品を上映することはどういうことなのか、という批判は当然あり得ます。
かつてこういうことは他の映画館でもあって、『ナムルの家』という従軍慰安婦をテーマにした映画を上映した際に右翼が押し寄せてきました。
また、南京大虐殺をテーマにしたある作品を中国から買って来た若松孝二さんは、腹に晒と週刊誌を巻いて、竹刀を持って劇場に立っていた、という話もあるぐらいです。
中日スポーツで「オウム真理教事件が映画になった」という記事が出て、それと共に猛烈なバッシングが始まりました。やはり、犯罪者を美化するのか、という内容で。
当時はTwitter等のSNSもありましたがそれほど普及はしていませんでしたが、今だったらもっとすごいバッシングがあっていたような気もします。」
木村「美化、という言い分に対しては、そもそも作品を作る時に、肯定も否定もしないようにしています。
ただ、自分にとってオウム真理教事件は事件が起きて2年目のところでストップしてしまっていた。なので、当時の人たちが何を感じていたのか、また、信者の中には自分がどういう逃亡生活を送っているのか知らないまま逃げていた人もいたので、そういうことについての取材はしても良いことだし、やはりすべきこと、とは思っていました。」
また、加瀬さんは、初披露となった東京国際映画祭での上映について
加瀬「東京国際映画祭では、海外の記者に反応がありました。彼らはオウム真理教の事件に興味を持って事件について調べていた、ということと、事件とこの映画の関係性についてはフラットに捉えてくれていたのです。」と語ると、
木村監督は、特に印象に残っている反応として、
木村「疲れている日本人の肖像が描かれているのがリアルだ、と何人もの海外の記者に言われたことでしょうか。フランスでは、大災厄の疲弊感として印象が強く、そこに注目して上映してくれようとしました。疲弊という言葉は東京国際映画祭の時に良く聞いた言葉です。」としました。
また、現在のバッシングの風潮については、
加瀬「日本の社会が抱えていた問題が一気に噴出したのが1995年。作品の公開が条件反射のようなものすごい数のバッシングを受けた、ということもわからなくはないです。事件が起きる理屈に個人の実感が追いつかない、ということが、事件の背景の説明を試みた作品に対するバッシングにつながったのではないか、と感じています。今の日本で同じことをしようとしたらもっとバッシングを受けたのではないのでしょうか。池に落ちた犬を棒で打つような条件反射的なバッシングをする風潮は強まっているのではないか、と思っています。」とし、
これを受けて木村さんは、
木村「2012年は死の匂いが濃かった印象があります。それが生きていることをひと際、感じさせることでもあったかと思います。その実感が3年、4年経つと同じ東京にいても薄まってくる。そして、大災厄の傷も知らない間に縫合されていく。その違和感を持ちながら、外から来るものに対してピリピリしている印象です。国政が変わってきた、ということもあるのかもしれませんが。」と語りました。
また、加瀬さんは、ポレポレ東中野でのトークイベントについても言及。
加瀬「最終的な宣伝の決断で、オウム真理教元信者をモチーフにした映画、ということを情報として打ち出しました。そして打ち出すのであれば当事者を呼ぼう、ということで、”ひかりの輪”代表である上祐史浩氏をお招きして、トークイベントを行いました。その様子はWebサイトに上がっていますので、ぜひお読み頂ければ幸いです。」
木村監督は以下のように振り返ります。
木村「上祐さんについては、構えることなく話して頂きました。ご本人は様々な葛藤があったのでしょうが、”騒がせてしまい、お詫びします”との最初の言葉が印象的でした。
そして、色々な話をしました。オウム真理教の元信者で、現実社会に戻った方やご結婚された方も多いことや、平田氏が大震災を契機として出頭された、という心情についてなども。最後に印象的だったのは、国の右傾化について触れられていたことです。当時の自分にはすぐにわかりませんでしたが2年3年経ってきて、上祐さんのおっしゃっていたことがわかってきて怖くなってきました。」
加瀬「上映に来て頂いた、”ひかりの輪”のみなさんとても穏やかな方々、というのが自分の印象です。宗教活動をすることは自由だし、人を助けたいと思うことも自分が助かりたいと思うことも自由。でもどこでどうなると、事件になってしまうのか。
Hさんは何でも聞いてください、ととてもオープンであったし、ユーモアもあった。
彼らと自分を隔てるものは何なのか。右か左か、と言った簡単な話ではもちろんない。この世の中には膨大なグレーの荒野が広がっていて、自分が何を拠り所として生きるのか。それを自分の信念として捉える人もいるだろうし、それを自発的に見つける人もいる。
でもそれが何もなかったとして、外に強烈な何かがあったら、そこに惹きつけられない、と言い切れる自信などやはりない。それは善し悪しの問題ではなくて。
そういうある種の怖さ、みたいなものは、95年、2011年よりも、2018年の今の方がとても感じています。鵺のようにとらえどころがない、というか。」
最後にお二人から『息衝く』の宣伝がありました。
木村「『へばの』構想時から、10年越しで撮りたかった映画です。青森県六ヶ所村から東京へ避難してきた母子の話で、東京で―新興宗教団体に庇護され政治活動に関わっていく、という物語になります。」
加瀬「主人公が三人います、同じ宗教団体で育った幼馴染です。一人の男性の主人公は「自分は他人の幸せのために生きられるか」ということ考え続けて「個」として生きようとし、もう一人の男性の主人公は宗教活動をして政党を作る、といったように「公」に自分を開くことで救済の道があるのではないか、と日々模索を続けます。
二人の男性が「個」と「公」に分かれゆく中で、一人の女性が揺れ動く、という物語です。24日(土)から公開になるのでぜひ観に来てください。」

【今後の上映スケジュール】
■2/24(土)~3/9(金) 20:30
■3/10(土)~16(金) 12:30
■3/17(土)~23(金) 20:50
※3/24以降 上映未定
■料金:1,700円
■場所:ポレポレ東中野(https://www.mmjp.or.jp/pole2/)