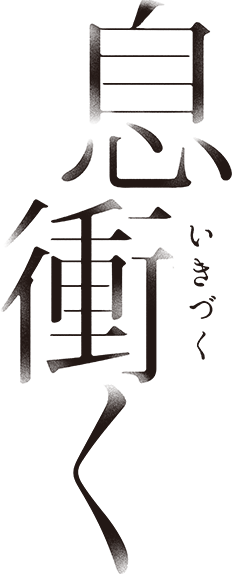上映日誌

【批評】あなたと私、そして出会いと別れ Resurrections vol.1-第5回

2018年批評誌『Resurrections vol.1』から第5回目、桑原 広考さん(『息衝く』プロデューサー)にご寄稿頂いた批評を掲載いたします。
あなたと私、そして出会いと別れ
桑原 広考(『息衝く』プロデューサー)
2018年6月。巷では欲望にしがみついた老人たちが面皮を保つために、人心を欺き続ける報せが後を絶たない。そんな世情の中、映画『息衝く』がこの7月から関西で順次公開されるにあたり、これを書いている。今年で私は40歳になる。恐らく多くの読者の方が知ることのない私自身の紹介を兼ねて、私と映画との関わりから語りたい。
東京近郊の衛星都市で生まれ育った私は、高校卒業後に紆余曲折を経て、改めて受験をした末に都内の大学に入った。そこで月並みだが映画研究会に所属した。転機は大学3年の時に訪れた。90年代から〝自前で映画を作り、自前で映画を見せる〞ことを信条としてきた先達との出会い。それが私のその後の生き方を大きく揺るがした。
翌夏、氷河期と言われた時節。周りの学生たちが就職先を求め駆け回るのを横目に、先達に師事し、友人たちと共に映画を作ることに没頭していた。初めて参加する映画の現場は、多くの躓きもあったが充足感と高揚感が沸々と湧き上がった。それはきっと体験したことがある人の多くが感じることだろう。この時にもたらされた価値観の転倒は、私にとっては発見だった。人と人との関係の中から自分という人間性が象られること。〝何者かになる〞よりも〝何事かをする〞という視点を持つこと。それらは私の生きる指針となっていった。必然的に参加した次の現場の初日は大学の卒業式と重なった。
〝自前で映画を作り、自前で映画を見せる〞ことを自らの手で実践する。そう望んだ私は真っ先に職に就いた。それは師から教えられた前提でもあった。つまりは生活と映画を両立するという課題に向き合う必要があったのだ。そうして日々模索していた私の元に、ある日突然分厚い企画書が届いた。先の現場で出会った男から送られてきたものだった。
彼も同様に生活と格闘しながら映画を志していたが、拠点としていた京都で思うように進んでいなかった。送られてきた企画は、彼の出生地である青森にある核施設を背景とした壮大な物語だった。自前で作るにはあまりに無謀で敬遠されても仕方がなかった。しかしそこには捨て身の覚悟が見られた。その証拠に、私が引き受けるなら上京すると彼は言った。すぐに返事を書いた。私も同じく無謀だったに違いない。その間にあったのは、なけなしの野心だったのかもしれない。唯一それが繋げてくれたのだろう。
彼は間もなく東京にやってきた。それまで共に映画を作ってきた人たちを巻き込み、製作に取り掛かった。協働と衝突を伴いながら、壮大な物語から半分ほどを抽出しなんとか形にした。出来上がった映画『へばの』は、社会の歪みに絡め取られ、悲しみを背負った男女の、別れと再会を描いた小さな物語となった。荒削りだったが、容易には折れない骨と芯があった。上映は全国各地や海外へと息長く広がり、深く浸透していくのが感じられた。いつしか彼は一人の映画監督になった。
野心を膨らませた私は東京を離れ映画を作り続けていた。彼も別の映画に取り組んでいたが、彼の中には置き去りにされたもう半分の物語があった。私もいつかそれに決着をつけなければならなかった。そして東北地方で起こった災害と事故を境に、本格的に動き出すことになった。それを成し遂げるには、新たな出会いや多大な支援が必要不可欠だった。製作は難航を極め、5年以上の歳月を要して映画は完成するに至った。彼にとっては10年を越える構想と願いが結実した。
『息衝く』を見て欲しい。幼い頃に出会った3人は、夢を見、誰かを信じ、あるいは裏切り、輝かしい喜びを分かち合い、やる瀬ない諍いに傷つき合い、時に別れ、時に出会う。それは何も特別なことではない。私にもこれまで訪れた時間であるし、あなたにも訪れたことがある、もしくはこれから訪れるかもしれない時間だろう。そういった誰もが通過する人生の交差から生じる、希望も絶望も、成功も挫折も、歓喜も悲哀も、あるがままに差し出し讃えようとする。それが『息衝く』で描こうとした根幹だと私は思っている。